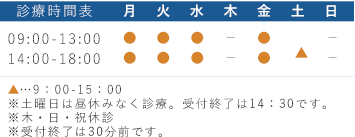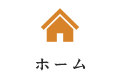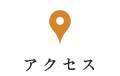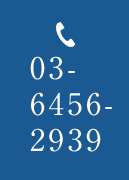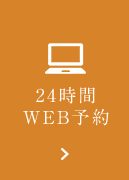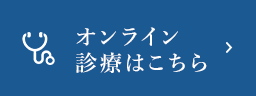糖尿病の方は、高血糖の状態が長く続くと、あるいは低血糖を繰り返すと、認知機能が低下しやすくなり、認知症を発症しやすいことが知られています。糖尿病の方はそうでない方と比べて、アルツハイマー病に1.5倍なりやすく、脳血管性認知症に2.5倍なりやすいという報告があります。また、男女差で見ると、女性の方が認知症のリスクが約2倍高いと考えられていますので、女性の糖尿病の方は特に要注意かもしれません。一方、認知機能が低下すると糖尿病薬の内服や自己注射、食事や運動の管理がうまくできなくなり、糖尿病の悪化につながることもあります。
そこで、認知症を予防するために、できる限り低血糖を起こさないように注意しながら、血糖値を良好に管理することが効果的であり、血糖値を良好に管理・維持することで、認知機能の改善も期待できるとされています。
なぜ、糖尿病になると認知症のリスクが高くなるのでしょうか。その主な要因として、次の3つが挙げられます。
① 血管の損傷(糖尿病による動脈硬化や脳血管障害)
高血糖により全身の血管がダメージを受けると動脈硬化を起こして血管が詰まりやすくなり、脳の血管にも影響が及びます。その結果、脳組織への血液の供給が滞り、神経細胞が死滅し、認知機能の低下を生じます。
② インスリン分解酵素の不足やインスリン抵抗性
認知症の中でも最も多い「アルツハイマー型認知症」は、「アミロイドβ」と呼ばれるたんぱく質が長年にわたって脳内に蓄積し、神経細胞が破壊される一因となることで発症すると考えられています。認知症の予防にはアミロイドβが溜まらないようにすることが大切ですが、実は糖尿病ではインスリンの作用低下によってこのアミロイドβの分解が妨げられ、脳内にアミロイドβが蓄積しやすくなり、その結果、認知症につながるということが、近年の研究で分かってきています。
③長期にわたる神経細胞のダメージ(高血糖や低血糖など糖代謝の異常)
糖尿病による高血糖状態や、治療などに伴う低血糖状態は、神経細胞に大きなダメージを与えます。すぐに影響があるわけではありませんが、40代から50代、60代と何十年も高血糖状態が続いたり、あるいは低血糖状態をくり返したりすると、たとえ動脈硬化や脳梗塞を発症しなくても、神経細胞が破壊されて認知症を発症するリスクが高くなります。これらの病態が糖尿病に特有な認知症で、糖尿病性認知症と呼ばれます。
いずれにせよ、高齢化に伴う糖尿病患者の増加や認知症の増加は私たち自身や家族の身近な問題です。心配な方はご相談下さい。